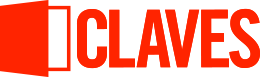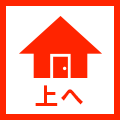
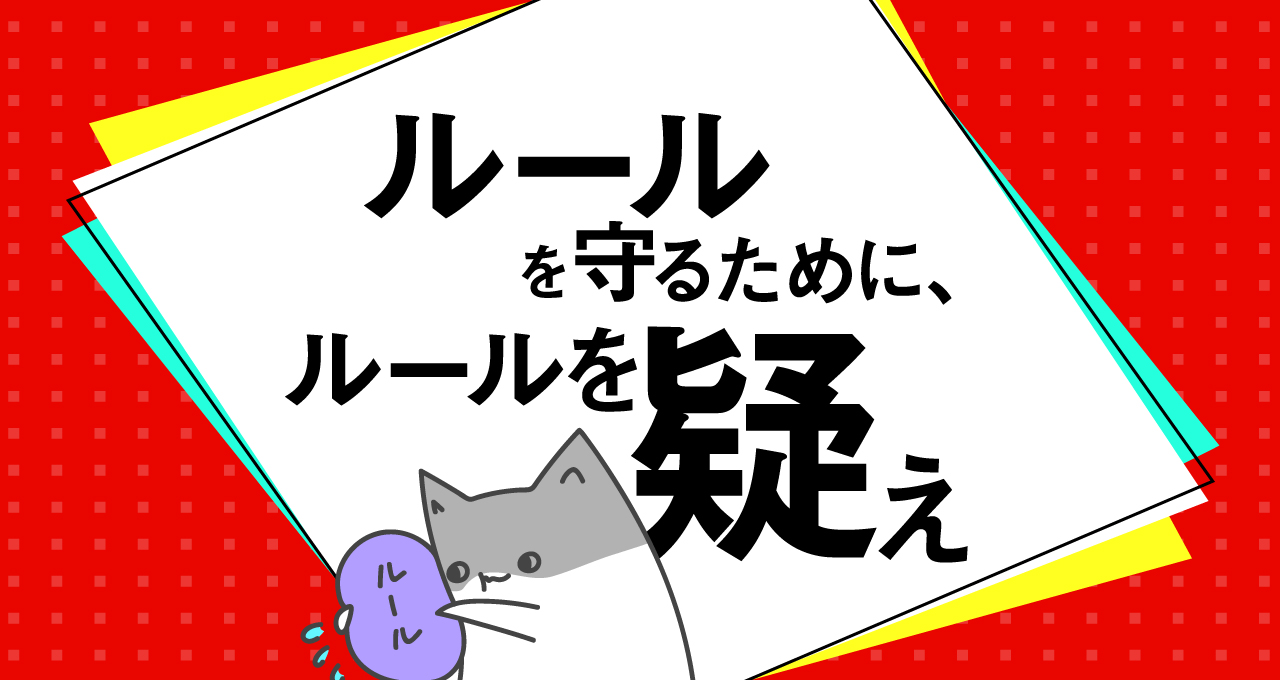
どーも。堀内です。
社会にも職場にも公園にも家の中にもルールがあると思います。最近はルールが増えすぎて世知辛いなぁと思うシーンもありますが、規約だったり、規則は多くあります。何かサービスを利用する際にも規約に承認していると思います。
法律だったり憲法だったり、自分には変えられないものは多くありますが、そこに対しては自然と守ることができているのではないかと思います。おそらく文化として、習慣として、守ることが当然の生活ができているのだと思います。
新しいものや、商売に関するものなどは変わっていくことも多いですし、業界の方などには重要なものになると思います。一般的にはニュースで知る程度のことが多いのではないでしょうか。

しかし、小さな組織やチーム、はたまた家族でのルールについてはどうでしょうか?決めた人が眼の前にいたり、決めた理由が明確にあったりすることが多いと思います。会社という組織の中では、大きくなるにつれて、その距離が生まれ、「何故そのルールができたのか?」その理由がわからなくなっていくものだと感じています。
会社を設立した当初、ルールに関係するメンバーは数人。家族と大差のない人数で、ルールに対しての疑問がある場合はすぐに聞ける環境でした。むしろ、ルールは少なく、チームの中でルールを作っていく、という過程が多かったと思います。
今年13期目に入りました。過去にあった失敗や経験からルールが作られていることが増えてきました。それが会社としての基礎となり、積み上げていくものになるとも言えます。大小問わず、後から入ってきた人、途中から参加した人が出てくる以上、ルールができた理由を知っている人は少なくなっていきます。
私も地域のお祭を統率する組織や、町会に参加をすることがありますが、いくつか積み上げられてきたルールがあることを感じます。
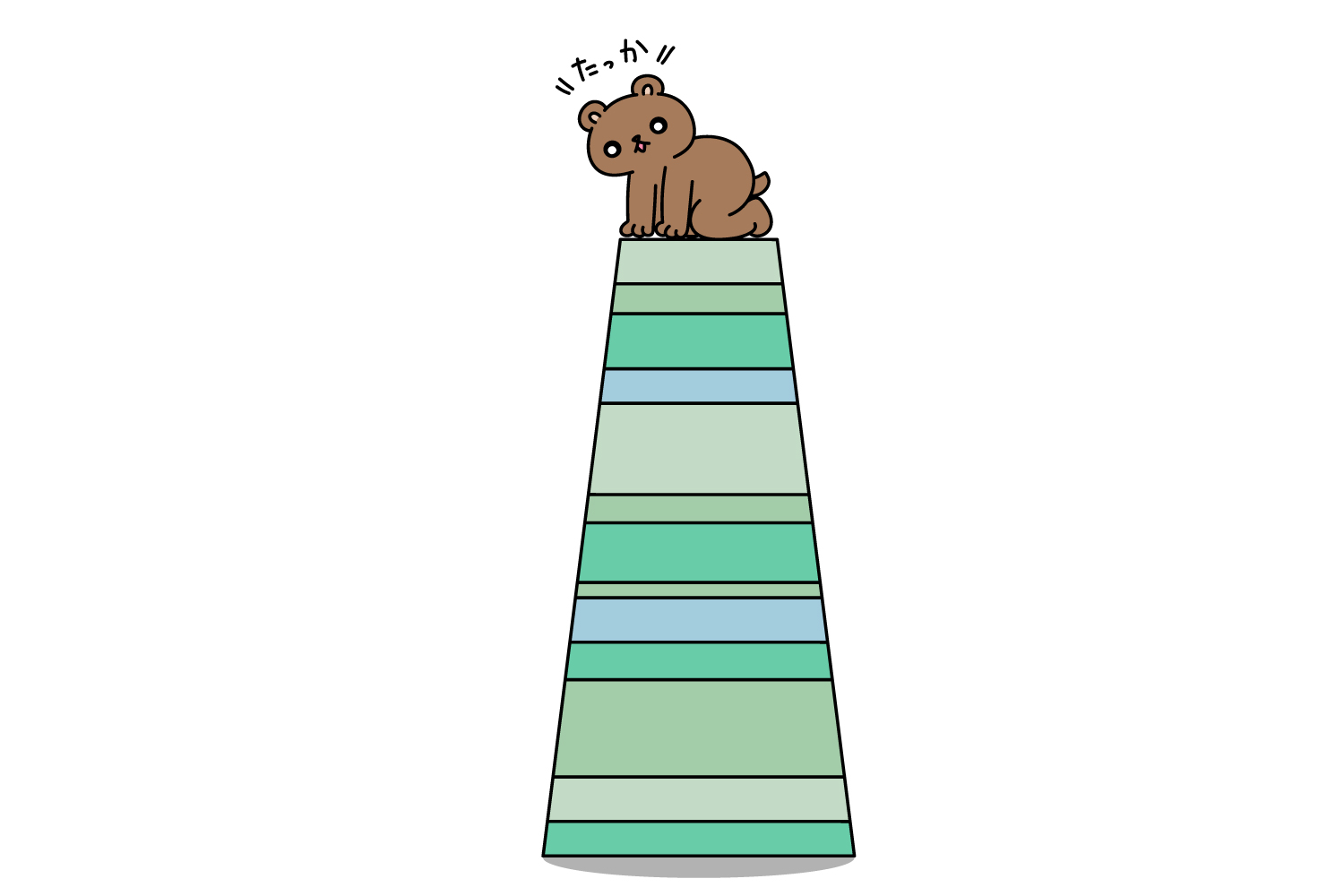
そういったシーンに直面したときに、ぜひやってもらいたいことがあります。 まずは、このルールが決まった理由を考えてみてください。なぜこのルールになったのか。自分が管理者側やずっとそこにいた人になったつもりで考える必要があります。正解にならなくてもよいです。考えることが大事です。
考えてみると、このような問題があったのだろう、という仮説が出てきます。
例えば、忘れないように前もってなにかメモを書くのがルールになっていたり、ものを管理する当番が決まっていたり、時間の設定が不自然に5分10分で刻んであったりするのが見えてきます。
そのうえで、実際に知っていそうな人に聞いてみましょう。おそらく古株と言われる人や、その組織の長に当たる人なんだと思います。その歴史を教えてくれると思いますし、ルールの意味だけでなく、組織のことを学ぶことができるでしょう。
学ぶことができたら、自分のものになったも同然で、自分がルールを決めた人(と同じ状態)になれると思います。そうなると、ルール以上にその作った意味を体現できる人になると思いますし、より良いルールを作ることにもつながると思います。
この”より良いルールを作れる状態”ができることが、さらなるチームの強化に繋がります。
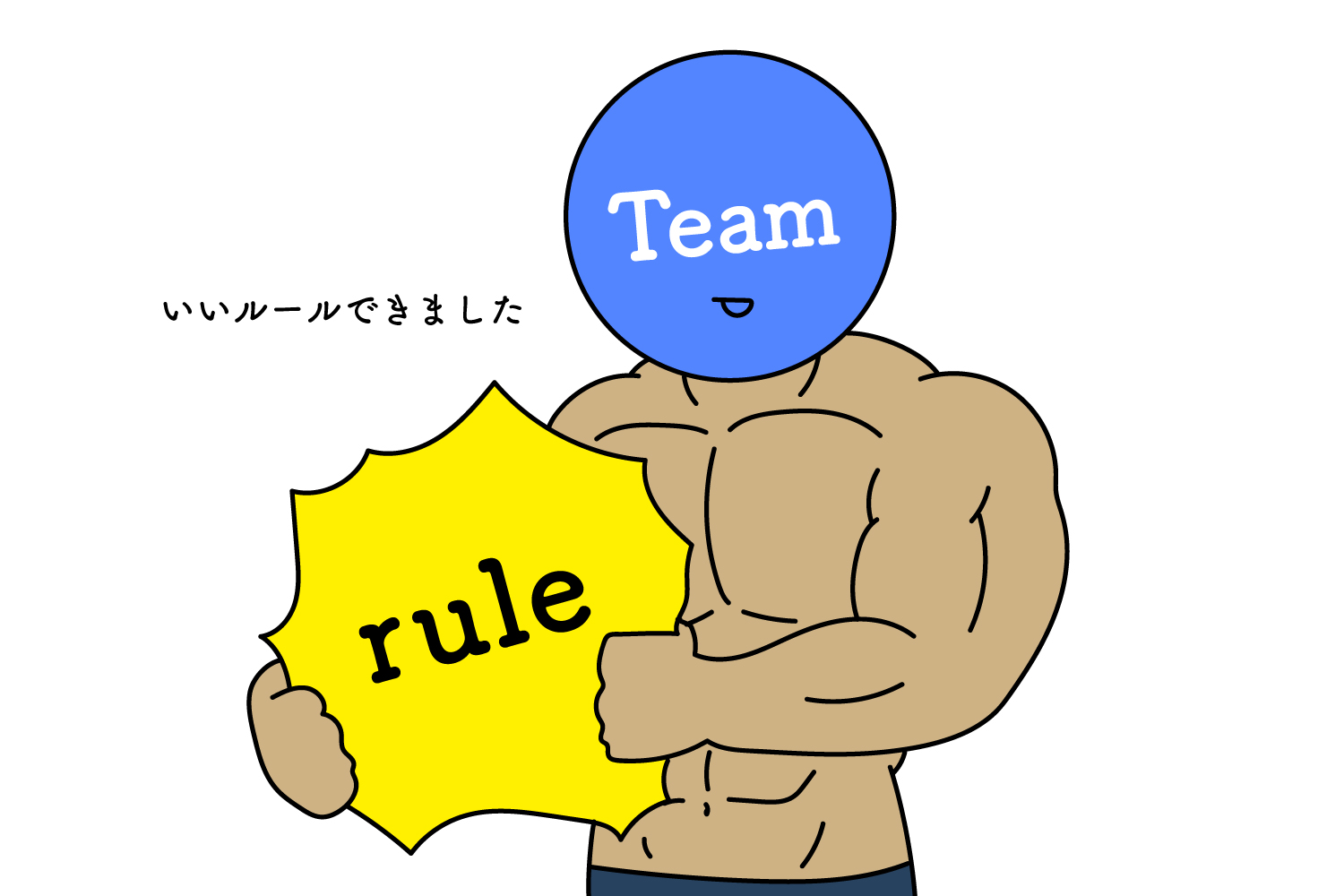
ルールを守ることは大事です。しかし、ルールを疑って、理解して、より良いものにしていくことができれば、組織としての強さが増します。むしろ、最初に作ったルールでそのままになっていると、意味のないものになりがちです。
30年前と同じルールのものがあったとして、インターネットやスマートフォンの登場に適しているでしょうか?AIを有効活用できているでしょうか?不変なものはあって良いと思いますが、変えることでよくなるものもたくさんあります。
家族のルールも年齢などで大きく変わっていくと思います。会社のルールも人数やフェーズで変わっていくと思います。
その変わっていく組織・社会の中で、自分が主体的に過ごせるように。のびのびと過ごせるように、ルールを疑ってみてはいかがでしょうか?
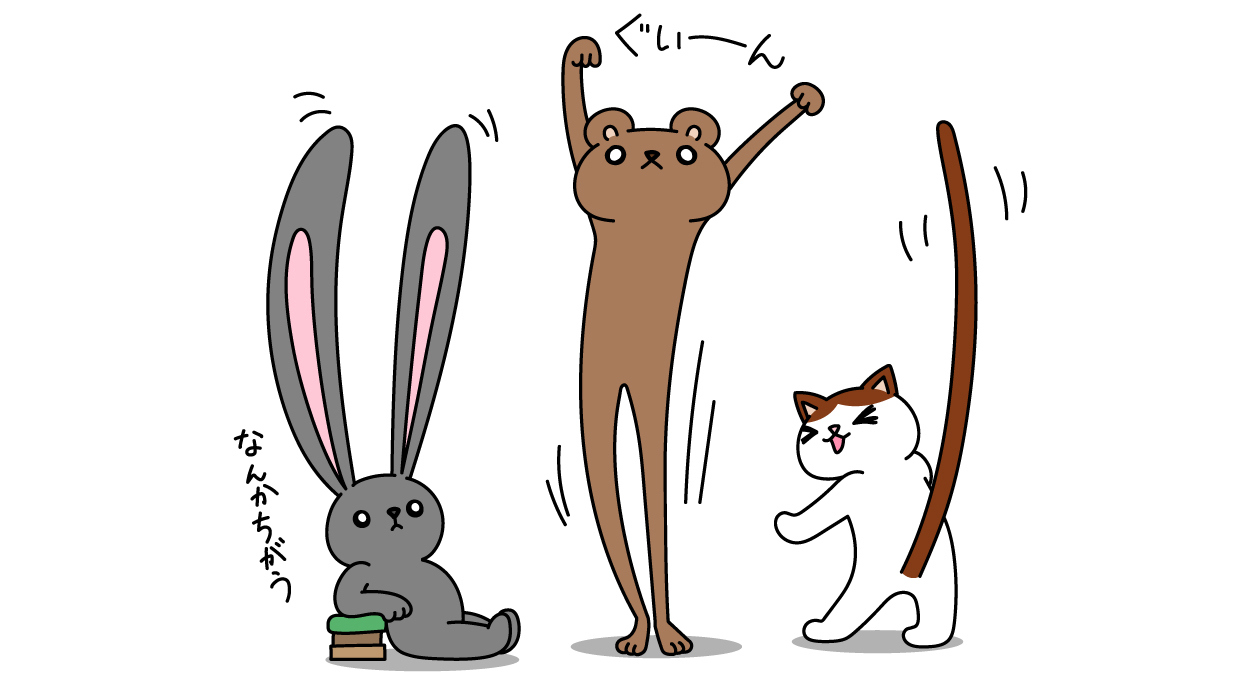
ではまた。
2025.04.10 堀内文雄(県が違うだけでもルールは違います。旅をしてみましょ)